History 東京団地冷蔵50年史
1930

1967年(昭和42年)
「東京団地冷蔵建物株式会社」設立
高度経済成長を迎えた昭和30年代。生活水準も「3種の神器」によって大きく変化し、その影響は食生活にも波及した。
電子レンジの普及により冷凍食品が台頭し、食卓に劇的な変化をもたらした時代である。
「流通業務市街地の整備に関する法律」の制定により「冷蔵業者が共同出資をして新会社を設立し倉庫の建設及び貸し付けを行う」計画が起案、実行されることになる。
電子レンジの普及により冷凍食品が台頭し、食卓に劇的な変化をもたらした時代である。
「流通業務市街地の整備に関する法律」の制定により「冷蔵業者が共同出資をして新会社を設立し倉庫の建設及び貸し付けを行う」計画が起案、実行されることになる。

1969年(昭和44年)
第1期建屋工事着工
都市部の流通事情、交通事情解消とともに冷蔵品の物流状況改善を目指して第1期工事が開始された。
建築面積は1棟あたり延べ1万2346㎡、庫腹は4棟合計で5万4400トンに達した。
1万トンでも超大型倉庫と称された時代に5万トンを超える規模を誇る冷蔵倉庫の建設に新たな社会インフラとしての期待が寄せられることとなった。
建築面積は1棟あたり延べ1万2346㎡、庫腹は4棟合計で5万4400トンに達した。
1万トンでも超大型倉庫と称された時代に5万トンを超える規模を誇る冷蔵倉庫の建設に新たな社会インフラとしての期待が寄せられることとなった。
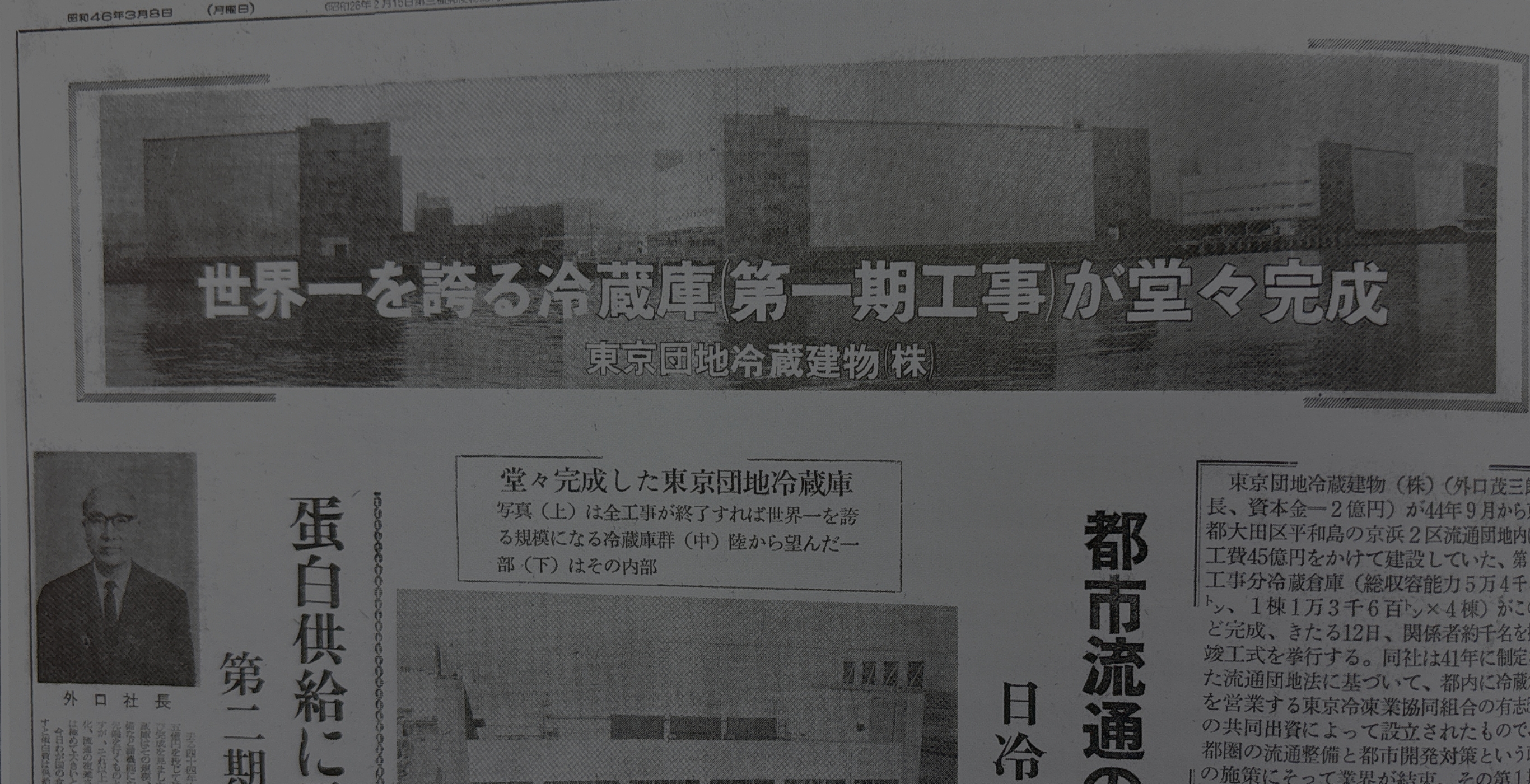
1971年(昭和46年)
第1期竣工
4棟合計5万4,400トンの収容能力
昭和46年、無事に完成を迎えた第1期に建設された倉庫は営業を開始。都心部の物流改善に大きく貢献したが、都内における冷凍品の年間総入庫量は増大を続けており、年平均で約5万トンの庫腹拡大が必要とされていた。
この様な状況の中で、早期に第2期の工事が計画された。
この様な状況の中で、早期に第2期の工事が計画された。

1972年(昭和47年)
第2期工事着工
第2期工事では4棟の倉庫の建設がスタートした。その増設により設備能力は6万5300トン、総計11万9700トンに達することとなり、大きな期待が寄せられた。
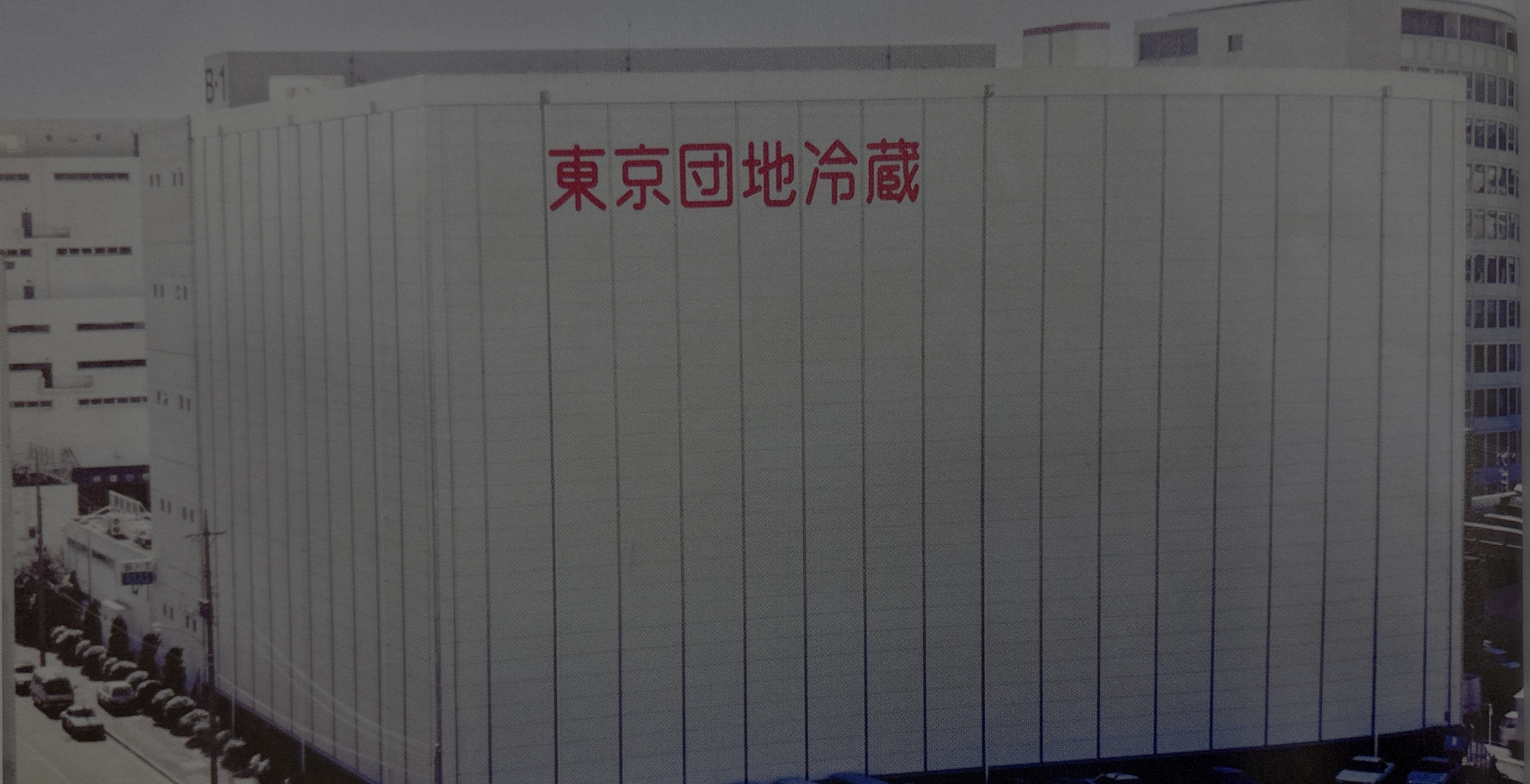
1974年(昭和49年)
第2期竣工
8棟合計11万9,700トンの収容能力
第1期工事のノウハウをいかした第2期建屋は設備能力の2倍強に達する21社、合計14万730トンの利用申し込みがあり、「均等割」と「協力度割」を考慮し借庫配分を決定した。
急拡大を続ける冷凍品物流を支える基盤として多くの企業に、また流通に貢献する拠点へと成長した。
急拡大を続ける冷凍品物流を支える基盤として多くの企業に、また流通に貢献する拠点へと成長した。

1975年(昭和50年)
第3期工事着工
流通業務地区における容積率の制限が200%から300%へ変更されたことにより、第3期建設計画が浮上。
物価の上昇により建設資材高騰の中ではあったが、借庫を希望する株主からの強い建設要望に応えるため第3期工事が実現することとなった。
物価の上昇により建設資材高騰の中ではあったが、借庫を希望する株主からの強い建設要望に応えるため第3期工事が実現することとなった。

1976年(昭和51年)
第3期竣工
9棟合計14万7,840トンの収容能力
昭和51年、約1年の建設期間を経て、第3期の冷蔵倉庫が営業を開始。収容能力は2万8140トン、第3期の稼働をもって総収容能力は実に14万7840トンに達した。第1期、第2期とは異なり、冷却方式は各階ユニット式を採用。今までの経験をいかした設備改善と衝撃振動対策にも取り組んだ倉庫となった。

2004年(平成16年)
最良の施設を目指して
高度経済成長にともなう畜肉類消費量が増加し、ハム・ソーセージなどの原料に加え「焼き鳥」に代表される加工品の取り扱いも徐々に拡大していった。品目の変化や量的な拡大は業務に様々な影響を及ぼし、日付管理、チルド化など高度な管理が必要となり、捌き場の低温化・ドックシェルター設置を実施し、品質管理の厳格化を行った。

2012年(平成24年)
再整備事業スタート(建替え計画開始)
平成11年、第1期工事の竣工からは28年が経過し、設備や機能の経年劣化も進み、各所機能に問題を抱えるようになっていたことから再整備や補強の計画が何度も議論されたが、コストや賃料面での事業性が認められず白紙に戻った。
再整備計画が思うように進まない中、平成23年に発生した東日本大震災で他の臨港区域は液状化が発生し営業に大きな支障をきたしたが、当団地の設備に大きな被害はなかったことで現有地での耐震面での優位性が示され、新冷蔵倉庫の建設計画が具体的に動き出した。
再整備計画が思うように進まない中、平成23年に発生した東日本大震災で他の臨港区域は液状化が発生し営業に大きな支障をきたしたが、当団地の設備に大きな被害はなかったことで現有地での耐震面での優位性が示され、新冷蔵倉庫の建設計画が具体的に動き出した。

2018年(平成30年)
新冷蔵倉庫竣工
2棟合計17万7,873トンの収容能力
新時代にふさわしい倉庫になるべく、今までのノウハウを最大限にいかした倉庫がついに完成。
安全・安心への配慮を重視し、特に東日本大震災の教訓をいかして耐震、高潮、津波に対して徹底強化をはかった。
また、新倉庫では大型コンテナが容易に入退場できる転回場と多くの大型車両向け待機場を設置するとともに、共同のコンテナヘッドを活用し、事前に登録された搬入データーにもとづいて効率的なつけ替えが可能となり、スムーズな搬出入と徹底したムダの削減を実現した。
安全・安心への配慮を重視し、特に東日本大震災の教訓をいかして耐震、高潮、津波に対して徹底強化をはかった。
また、新倉庫では大型コンテナが容易に入退場できる転回場と多くの大型車両向け待機場を設置するとともに、共同のコンテナヘッドを活用し、事前に登録された搬入データーにもとづいて効率的なつけ替えが可能となり、スムーズな搬出入と徹底したムダの削減を実現した。

2025年(令和7年)
さらなる成長と発展
食品物流の要となる企業を支えていく物流拠点としてただ冷蔵設備を提供するだけではなく、社会的責任を果たしていくことが我々の使命です。
50年間蓄積してきた知見をいかしながら、これからの物流を、そして人々の豊かな生活を支えるため、さらなる成長と発展へ向けてまい進していく所存です。
50年間蓄積してきた知見をいかしながら、これからの物流を、そして人々の豊かな生活を支えるため、さらなる成長と発展へ向けてまい進していく所存です。
